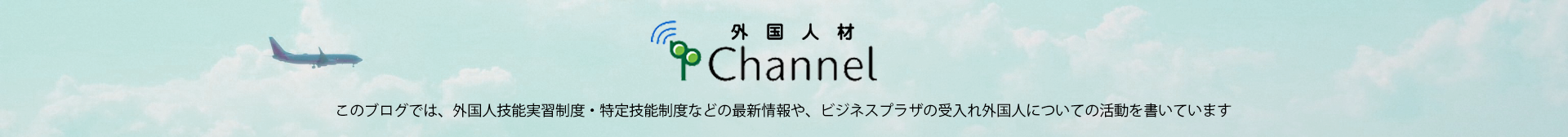ホーチミン面接に行ってきました。気温は30度以上で日中は暑いですが、夜はすごしやすい気候でした。 企業様が目を引く実習生はやはり愛嬌があり、最後まで諦めない姿勢を見せてくれる実習生です。 愛嬌は、パートの方と仲良くできる…
続きを読む2019年 11月 の投稿一覧
実習生の寮について
実習生の寮についてはいくつかの決まりがあります。 その中で注意すべき点を列記していきましょう。 まず、運用要領の中で以下の決まりが定められています。 (1)宿舎を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大き…
続きを読むハノイ面接
ハノイ面接に行ってきました。 滞在中は毎日雨、温度が上がらず快適に過ごせました。 今回の職種は漬物製造。 面接と計算テストの他に実技テスト(手先の器用さテスト)がおこなわれました。 箸で豆を皿から皿へ移動させる作業とハサ…
続きを読むベトナム 編み笠
ベトナムの農村風景といえば 編み笠をかぶったお父さんお母さんが 手作業で田植えをしている姿が目に浮かびます。 かと思えば 美しい鮮やかな「アオザイ」を着た美女も さりげなく編み笠をかぶって ポスターの中にい…
続きを読む外国人実習生にはわかりやすい日本語で
先日、とある会社様の実習生の配属を行いました。 会社様としては、これまで何十名も実習生を受け入れて頂いていましたが 今回の事業所では初めての受け入れとなりました。 当然、事業所は担当者の方も含め、実習生と仕事をするのは初…
続きを読む外国人実習生の近況(11月の定期巡回にて)
外もすっかり暗くなってしまった夕方、実習生の定期巡回で秋葉原へ行きました。 こちらの会社様では現在ベトナム人実習生が13人働いています。 仕事を終えた実習生が次々と事務所へ集まってきます。 最近は急に寒くなり、みんなしっ…
続きを読む建設分野における技能実習制度について
2020年1月1日以降、建設分野の技能実習生を受け入れ予定の企業様は必見です。 下記は国土交通省から抜粋した文書です。 令和元年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び…
続きを読む