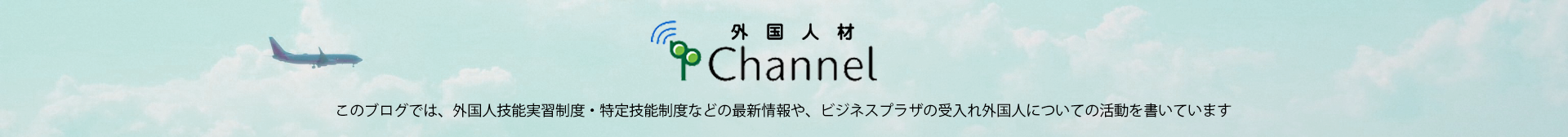実習生の成長が実感できる瞬間は帰国です。大体の実習生は今後の目標をもって帰国をします。 最近では特定技能で戻って来たい実習生が増えています。 オリエンテーションを行い、ゴミ袋のセットの仕方、掃除機の使い方な…
続きを読む2019年 7月 の投稿一覧
実習生の転職・転籍について
技能実習生から転職や受入企業から組合の変更などについて相談を受けることがあります。 技能実習生の可否や方法などについて触れておきます。 ★実習生の転職 ・1号および2号実習生については原則認められておりません。 3号は可…
続きを読む「日本文化の体験」夏祭り
今日は恒例の夏祭りです! 実習生寮にて行います! 実習生の皆さんも 会社様も 私たち監理団体も 毎年この日を楽しみにしています。 たこ焼き 流しそうめん 綿あめ 水ヨーヨー 今回は お習字も。 実習生の勉強の一つである「…
続きを読む水産加工の技能評価試験
先日は非加熱性水産加工食品塩蔵品製造の技能評価試験を行われました。 学科試験、実技試験の順となります。 まず学科試験は筆記試験と原料魚介類の選定、包丁選定があります。 その後に行われる実技試験は作業者の衛生管理、器具の衛…
続きを読むJITCO日本語指導セミナー
先月、JITCO主催の日本語指導セミナーに参加してきました。 私は、実習生の入国後講習中に行う組合講話を担当していますが、 入国して間もない実習生は日本語能力もまだ低く、コミュニケーションを取るのも難しい為、 どうすれば…
続きを読むベトナム人実習生 ハノイ面接
ハノイにて実習生の面接に同席しました。 この日ハノイの温度計は37度でしたが、現地職員が言うには実際は40度以上。 じっとしていても汗が出る中、まず体力テストがおこなわれました。 腕立て伏せに、荷物の上げ下げ、 辛…
続きを読む日本語能力試験
先日の7月7日(日)に2019年度 第1回日本語能力試験が開催されました。 日本語能力試験とは1984年から開始された、日本語を母国語としない人たちの日本語能力を測定し 認定する試験です。 試験開始初年度は、世界15ヵ国…
続きを読む