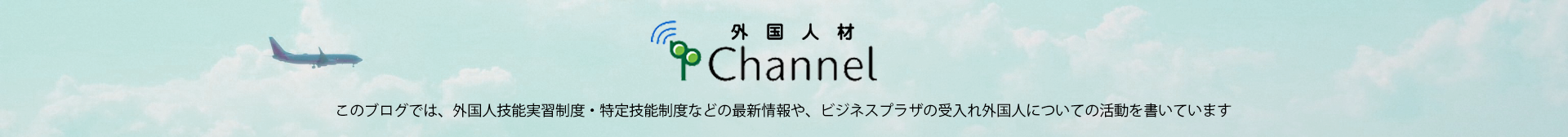外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能移転を図り、途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。実習実施機関は技能実習を通じて技能実習生に技能を修得させるという重要な役割を担うため、技能実習生の受入れ条件…
続きを読む2017年 1月 の投稿一覧
外国人技能実習機構を設立?外国人技能実習適正実施法の内容
外国人技能実習制度は、技能実習生への技能移転を図り、途上国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。しかし、一部の受入れ機関は本来の目的を理解せず、技能実習生を安い労働力として扱っているケースも少なくありませ…
続きを読む【外国人技能実習制度】技能実習1号から2号への移行対象職種
現行の外国人技能実習制度における技能実習は、入国1年目の技能を修得する活動(在留資格「技能実習1号」)と、入国2~3年目の修得した技能に習熟する活動(在留資格「技能実習2号」)に分かれます。今回は、技能実習1号から2号へ…
続きを読む外国人技能実習生が介護士に!外国人技能実習制度に介護が追加
総務省統計局が平成28年9月18日に発表した「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」によると、日本の65歳以上の高齢者人口は3461万人、総人口に占める割合は27.3%に達します。 しかし、介護現場は深刻な人材不足に…
続きを読むここがポイント!日本語が出来るベトナム人を採用するコツ
近年、日本で就労する外国人労働者数が増えていますが、特にベトナム人労働者数の増加が顕著です。厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、平成27年10月末現在、中国の32万2,545人(外国人労働者全体の…
続きを読む外国人の就労ビザ申請は何をする?日本で働ける就労ビザの取得方法
従来は外国人を雇用する企業は限られていましたが、最近では職場の活性化や海外展開の加速化を目的として外国人を受入れる企業が増加しています。優秀な外国人材を見つけ、雇用するときは就労ビザを取得しなければなりません。今回は外国…
続きを読む配属
先日、ホーチミンから入国した6人が日本での1ヶ月間の講習を終了し、会社へ配属となりました。 さらに寒い環境での生活に、不安が募るようでしたが、雪を見て感動していました。 仕事の説明をベトナム語の通訳を通して受けましたが、…
続きを読む外国人の雇用状況は?外国人労働者数の推移と現状
日本における労働力人口(15歳以上の就業者と完全失業者を合わせた数)は、平成27年度平均で6,598万人、前年と比較して11万人増加(3年連続増加)しました。しかし、生産年齢(15歳以上65歳未満の人口層)における労働力…
続きを読む建設機械施工職種(締固め作業)の技能検定
今日は建設機械の1つ、ロードローラーでの技能検定です。 本人はとても緊張しています。 「前ヨシ!左ヨシ!」と緊張しながらも一生懸命声を出して、真剣に臨んでいます。 検定に合格することが、2年目の技能実習への必須となってい…
続きを読む外国人技能実習生の雇用保険・健康保険はどうなる?保険のあれこれ
安心して働く上で、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)は欠かせない制度です。外国人技能実習生についても、これらの保険は適用されるのでしょうか。今回は雇用保険や健康保険などの公的保険と、外国人技能…
続きを読む